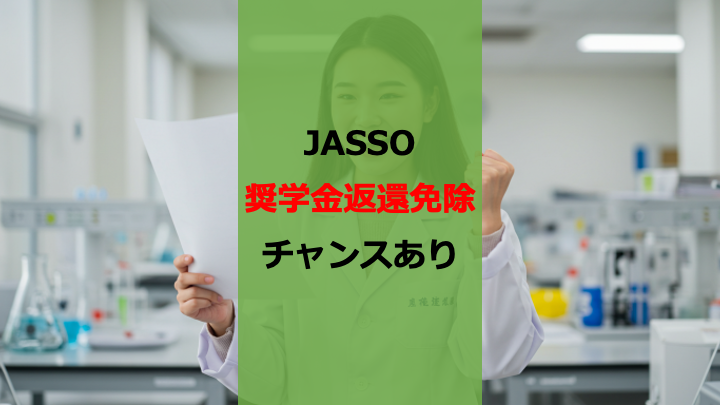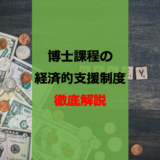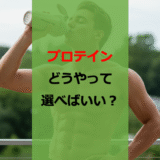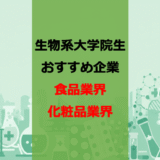こんにちは。ぱにです。

医学系の研究室で博士号取得を目指しています。
この記事では、大学院進学に向けて奨学金の利用を検討している方に向けて、JASSO奨学金の返還免除制度について解説していきます。
お金は借りたら返すもの。それは、誰もが知る常識です。
奨学金も例外ではありません。名前こそ「奨学」と謳っていますが、実際には借金と同じです。
そうしたマネーリテラシーを持って、奨学金の借り入れを判断できることは、とても大切なことです。
ですが、一度借りた奨学金を返さなくて済むケースがある、というのはご存知でしたか?
しかも、それは成績トップだけ、一流大学だけに限った話ではありません。
大学院生なら、誰にでも狙えるチャンスがある制度なんです。
ぜひこの記事を最後まで読んで、返還免除を狙うための戦略の参考にしてみてください。
本記事は、JASSO奨学金の返還免除制度について紹介するものであり、奨学金の借り入れ自体を推奨するものではありません。
借り入れには将来的な返済義務が伴うため、よく検討した上で利用をご判断ください。
JASSOの返還免除制度とは?
この記事における「返還免除制度」とは、JASSO(日本学生支援機構)の第一種奨学金における「特に優れた業績による返還免除」を指します。
大学院で第一種奨学金の貸与を受けた学生であって、貸与期間中に特に優れた業績を挙げた者として日本学生支援機構が認定した人を対象に、その奨学金の全額または半額を返還免除する制度です。
学問分野での顕著な成果や発明・発見のほか、専攻分野に関する文化・芸術・スポーツにおけるめざましい活躍、ボランティア等での顕著な社会貢献等も含めて評価し、学生の学修へのインセンティブ向上を目的としています。
貸与終了時に大学に申請し、大学長から推薦された人を対象として、本機構の業績優秀者奨学金返還免除認定委員会の審議を経て決定されます。
特に優れた業績による返還免除の概要 | JASSO 概要より引用
対象となる学生と奨学金の種類
JASSO(日本学生支援機構)の返還免除制度は、「第一種奨学金」を利用している大学院生(修士・博士)が対象です。
JASSOの奨学金には、主に以下の2種類があります。
| 種類 | 利子 | 特徴 |
|---|---|---|
| 第一種 | 無利子 | 成績・家計に関する選考条件が厳しい |
| 第二種 | 有利子 | 金額の自由度が高く、比較的通りやすい |
第一種奨学金は選考が厳しく、学部時代には借りられなかったという方もいるかもしれません。
しかし大学院生の場合は、親の年収ではなく、本人の収入で審査されるため、ハードルは大きく下がります。
そのため、多くの大学院生が、ほぼ確実に第一種奨学金を借り入れることができます。

第二種は返還免除の対象外なので注意!
免除の種類と倍率の実態
免除には、借りた奨学金の100%が免除となる「全額免除」と、借りた奨学金の50%が免除となる「半額免除」があります。
JASSOの公式HPで公開している情報によると、返還免除候補者のうち約3割が返還免除を認定されています。
さらにそのうちの約25%が全額免除を勝ち取っているようです。

僕は修士課程で第一種奨学金をお借りし、半額免除の認定をいただけました。
「誰でも狙える」と言える理由
ここで重要なのは、この免除制度は全国一律の競争ではないという点です。
免除候補者は各大学ごとに選出されるため、大学内での相対評価で推薦されるかどうかがカギになります。
つまり、全国トップクラスの成績でなくてもOKで、自分の大学・研究科の中で一定の研究成果を出していれば十分狙える、ということになります。
戦略的に動けば、あなたにも手が届く現実的なチャンスなのです。
返還免除の評価基準
JASSOの公式サイトでは、返還免除のための評価項目と基準が公開されています。
大学院生が意識すべき主な評価項目を、公式の番号に沿ってご紹介します。
1. 学位論文その他の研究論文
とにもかくにも、論文です。
どの分野であっても、論文の本数は返還免除の審査において強い武器になります。
たとえば生命科学系では、修士課程で1本でも論文があれば、返還免除にかなり近づくと言っても過言ではありません。
学会発表もこの項目に含まれます。
論文化が難しくとも、積極的に学会に出て発表する姿勢は、確実に評価につながります。
4. 著書,データベースその他の著作物
一般的な大学院生だと、なかなか論文以外で書き物をすることは少ないかもしれません。
ただし、実験医学などの専門誌に寄稿したり、書籍の一部を執筆する機会があれば、ここに該当する可能性があります。
とはいえ、この項目で大きな差がつく可能性は低いと考えてよいでしょう。
5. 発明
分野によっては、研究成果を特許出願に繋げるケースは珍しくないかもしれません。
研究室の知財戦略的に、論文化よりも特許を優先するような状況もあるでしょう。
そうした場合でも、発明の実績が返還免除の加点対象になるため、チャンスは十分にあります。
特許が狙えるテーマに取り組んでいるなら、ぜひ積極的にアピールしていきたい項目です。
6. 授業科目の成績
大学院生の講義は、学部生とは違ってかなり甘めの成績をつけてくれると思います。
特に研究室の教授が成績をつける科目は、比重が大きい割に、真面目に取り組んでいれば高評価がつくことが多いはずです。
そのため、授業の成績で差がつくかはかなり微妙なところではあるものの、この些細な評価の差が最後に結果に直結する可能性は大いにあります。
履修はミスなく、テストやレポートは抜かりなく。確実にいい成績を収めておきましょう。

ちなみに、僕は当時、研究室の教授と揉めたおかげで、研究室の成績を下げられていました。
こういうときにも教授との関係づくりは大事ですので、皆さんはお気をつけて。
7. 研究又は教育に係る補助業務の実績
リサーチアシスタント(RA)やティーチングアシスタント(TA)としての活動が、が実績として評価されます。
タイパのいいちょっとしたアルバイトになるので、大抵の大学院生は申し込んでいる印象です。
そういう文化が醸成されていない研究室でも、教授に相談しTAとして授業の準備の手伝いなんかをすれば、実績として十分なのではないかと思います。
こうして並べてみると、やはり評価の軸は研究業績にあります。
論文と学会発表、この2つが最も大きく差を生むポイントです。
学振(DC)ほどガチガチの業績を求められるわけではありませんが、狙って業績を積む意識は返還免除にも通用します。

僕は修士課程修了時、共著の論文が1本と学会発表が6-7回ほどの業績でした。
学振を考えると微妙な業績ですが、どうにか半額免除にはなるくらいの業績だったようです。
リスクとリターン
(リスクやリターンといった言葉が不適切でしたらごめんなさい。)
繰り返しになりますが、奨学金は本質的に借金であり、当然ながらリスクのない制度ではありません。
たとえば第一種奨学金で月8万8千円を2年間借りれば、卒業時点で約200万円の債務を抱えることになります。
返還免除が得られなければ、その全額を自分で返済していく必要があり、延滞すれば延滞金が発生し、信用情報に傷がついたり、最悪の場合は法的措置に発展する可能性もあります。
免除が叶わなかった場合の返済計画は、貸与を受ける前や在学中の段階から検討しておくべきでしょう。
さらに、返還免除を目指すには研究業績の積み重ねが求められますが、研究というものは努力だけでは思い通りに進まないことも多いものです。
実験が予定通りに進まない、学会や論文の採択が間に合わない、あるいは体調や人間関係といった予測不能な要素に左右されることもあります。
そういった意味で、この制度には成果の不確実性というリスクも内在しています。
とはいえ、それでも狙う価値は十分にあります。
第一種奨学金は無利子で、実際に約3割の学生が何らかの返還免除を受けており、免除が実現すれば、実質的には給付型奨学金と同等の経済的メリットが得られます。
免除された金額には課税もかからず、税負担の心配もありません。
また、返還免除の実績そのものが、今後の履歴書や自己PRで活用できるアピール材料となるでしょう。
返還免除は全国一律の競争ではなく、大学ごとの推薦制で行われるため、自分の大学や研究科の中で成果を出すことで十分に狙えるチャンスがあります。
その意味でも、多くの大学院生にとって、この制度はモチベーションを高めるきっかけになり得るはずです。
返還免除申請の方法と注意点
JASSO奨学金の返還免除は、全国一律の応募ではなく大学ごとの推薦制で行われます。
そのため、申請も各大学を通じて行う必要があります。
申請時期の目安としては、卒業年度の11月〜12月ごろに要項が掲示され、12月〜1月ごろに提出期限が設けられるケースが一般的です。
申請にあたっては、JASSOの公式サイトに掲載されている評価項目に基づいた申請書のほか、それらを証明する資料、さらに指導教員による評価書を提出します。
こうした案内は学内掲示やポータルサイトで静かに公開される場合が多く、強いアナウンスを期待するのは禁物です。
必ず自分の大学の奨学金関連のWebページを定期的にチェックしておきましょう。
なお、これは奨学金の借り入れ時にも共通して言えることですが、奨学金制度は締切に非常に厳密です。
提出忘れや遅れが致命的になるため、事前の情報収集と準備を怠らないようにしてください。
また、返還免除制度は博士課程の学生にも適用されますが、令和5年度以降は一部例外があります。
JSTが実施する「次世代研究者挑戦的研究プログラム」や「大学フェローシップ創設事業」、「AI人材育成プログラム」といった支援を受けている博士課程学生は対象外となりますので、自分の支援制度の条件をよく確認するようにしてください。

博士学生の方は、きっと研究奨励費が支給される経済的支援を勝ち取れるはずです!
以下のページも参考にしてみてください。
まとめ:JASSO奨学金の返還免除は誰にでもチャンスがある
この記事では、JASSO第一種奨学金の返還免除ついて解説しました。
もちろん、奨学金の借り入れは慎重に判断すべきです。
ただあくまで一個人的には、返還免除まで視野に入れて戦略的に借りるのであれば、この制度はローリスク・ハイリターンの選択肢として大いに活用する価値があると感じています。
だからこそ、この制度を知った上で、自分なりのスタンスで挑戦をおすすめしたいと思います。
では。