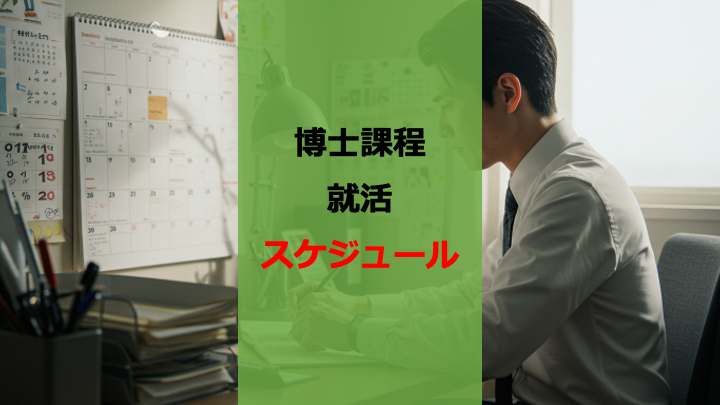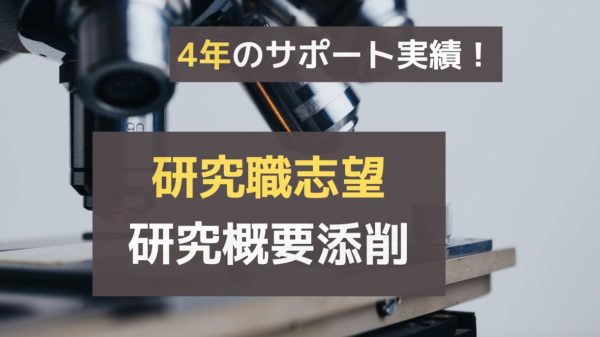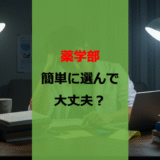こんにちは。ぱにです。

医学系の研究室で博士号取得を目指しています。
この記事では、博士課程で民間企業への就活を考えている方向けに、博士学生の就活スケジュールについて、僕の体験をもとに解説していきます。
- 博士学生はいつから動き始めればいいの?
- 修士と一緒に就活をやるの?
- 周りにロールモデルがいなくて不安。。。
こんな疑問や悩みを抱えている博士課程の方は、きっと少なくないはずです。
僕自身、26卒として博士課程の就活に挑みましたが、周囲に相談できる人はほとんどおらず、情報も断片的で、手探りの中、孤独な戦いを強いられました。
この記事では、そんな経験をふまえて、どの時期に何をやるべきかを中心に、自分自身の反省点や気づきも交えながらお伝えできればと思います。
以下の記事も参考にしてみてください。
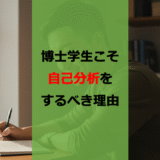 【キャリアづくり】博士学生こそ自己分析をするべき4つの理由【自分と向き合う】
【キャリアづくり】博士学生こそ自己分析をするべき4つの理由【自分と向き合う】
※この記事にはアフィリエイトリンクが含まれます。
ざっくりとした就活スケジュール
博士課程の就活スケジュールは、目指す進路(アカデミア・企業・留学など)によって大きく異なります。
また、同じ企業就職であっても、推薦やスカウトといった逆指名型で決まるケースも多く、その場合は就活の時期やプロセスも変則的になります。
今回は、企業の採用活動に自らエントリーして就職を目指す、3年制の博士学生を想定し、スケジュールの全体像をお伝えします。
研究との両立は大前提として、就活に関する部分のみを抜き出して整理したものというスタンスでご覧ください。
| 具体的な動き | 時期 | |
|---|---|---|
| Phase1:自己理解・情報収集 | ・自己分析 ・業界研究・企業研究 ・インターン参加(博士向け) ・OB・OG訪問・キャリア相談 ・就活サイト登録 ・英語(TOEICなど)・プログラミング・資格等の研鑽 | ・できるだけ早く(M1・M2・D1春〜冬) ※就活が終わるまで継続的に行う |
| Phase2:選考準備・書類準備 | ・研究概要の作成 ・自己PRの作成 ・成果一覧の整理 ・ポートフォリオの作成 | ・D1冬〜D2春 |
| Phase3:エントリー・選考序盤 | ・企業へのエントリー ・企業説明会 ・自己PR・志望動機のブラッシュアップ ・ES設問の回答 ・企業スカウトからの対応 ・技術面接対策 ・夏インターン参加(全学年向け) ・SPIなどのWebテスト対策 | ・D2春〜秋 |
| Phase4:最終選考・内定獲得 | ・オンライン面接・対面面接 ・最終面接 ・内定承諾 | ・D2夏〜D3春 |

人によって取り組む内容や時期は異なってくるはずです。自分に合った形で臨機応変に対応していくことが大切です。
このスケジュールを見て、動き出しが早すぎでは、と感じた方もいるかもしれません。
でも、博士課程の研究生活は、ご存知の通り、本当に忙しいんです。日々の実験・解析・論文執筆に追われる中、いきなり就活のタスクを追加すれば、何かを犠牲にせざるを得ない状況になるのは目に見えています。
だからこそ、早めに動き出して、少しでも心と時間に余裕を持っておくことが大切です。

これは賛否あるかもしれませんが、たとえ博士進学を決めていたとしても、修士のうちに一度就活を経験しておけばよかったと今は思っています。
人生経験としてももちろん、情報収集や就活全体の流れをつかむこと、面接やグループディスカッションの感触を知ることにおいて、実際に動いてみることの価値は大きいと感じます。
Phase1:自己理解・情報収集
忙しい博士学生にとって、このPhase1は、最悪やらなくても就活はできると疎かにしがちです。
でも、納得感のある企業選びや、自分に合ったキャリアを描くためには、このフェーズが土台になります。
ここであげるタスクは、どれも今すぐにでも始められることばかりです。
選考本番が始まるまでに、計画的に取り組むことを強くおすすめします。
自己分析
すでに別の記事でも書いていますが、僕は博士学生こそ自己分析をやるべきだと思っています。
その理由については、そちらで熱く語っていますので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。
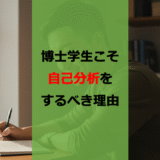 【キャリアづくり】博士学生こそ自己分析をするべき4つの理由【自分と向き合う】
【キャリアづくり】博士学生こそ自己分析をするべき4つの理由【自分と向き合う】
自己分析は、何を目指せばいいのか分からず、終わりが見えないと感じて、なんとなく敬遠されがちです。
でも、就活における自己分析の目的は、実はとてもシンプルです。
- 自分の強みを知ること
- 自分に合った環境を知ること
- そして、それらを言語化できるように準備すること
博士学生はもちろん、大学院生というのは、社会に出るまでに多くの時間と労力を費やしてきています。
できるだけ回り道をせずに、自分に合う企業を見つけたいと考えるならば、「とりあえず有名企業」ではなく、入社後にどう活躍できるかまでを見据えた選択が大切です。
だからこそ、丁寧で堅実な自己分析が、納得感のある就活に直結します。これは、僕自身が就活を経験して強く実感したことでもあります。
業界研究・企業研究・OB・OG訪問・キャリア相談
まず大切にしたいのは、視野を広げるということです。
就活生というのは大概、やりたいことが明確に定まっていません(むしろ、明確すぎる人はアカデミアや起業に進むべきだと思います)。
そのため、自分の専門と企業の事業内容が一致しているかどうか、というだけでいきなり候補を絞るのは、視野を狭める原因になります。
初期段階では、特定の分野や企業に絞り込まず、興味を持った分野を幅広く調べてみるのがおすすめです。
もし、身近に話を聞ける先輩がいるなら、OB・OG訪問を積極的に活用してみてください。
自分と近い経歴を持つ人のキャリアは、研究と企業のつながりや実際に働く環境を考えるうえでも、非常に参考になるロールモデルになると思います。
また、大学のキャリアセンターやアカリクの博士向けキャリア相談を利用することで、無意識のバイアスから離れ、意外な業界や職種に目を向けるきっかけにもなるはずです。
企業をある程度絞り込んできたら、企業研究にしっかり取り組みましょう。
企業の強み、価値観、今後の展望などは、公式に発信されている資料や企業HPから徹底的に調べ上げます。

ここはひとつ、博士学生の情報収集能力の腕の見せ所です。
なぜその企業で自分の強みが活かせるのか。なぜその企業でなければならないのか。自分と企業がどこで共鳴するのか。
こういった問いに、具体性と説得力をもって、美しく言語化できることを意識して、企業研究を進めていくといいと思います。
就活サイト登録
まず何よりも最初に、就活用のメアドを作ってください。大量のメールによって大事なメールが流れます。
実際に僕が登録していた就活サイトを紹介します。
- アカリク
大学院生や理系学生に特化した就活サイトです。
アカリクイベントでは、メーカー・IT・コンサル業界を中心に、大学院生を求める企業と出会うことができるイベントを主催していて、博士課程Expoといった博士学生向けのイベントも積極的に開催しています。
またアカリク就職エージェントでは、大学院出身のコンサルタントに就活相談をして、面接対策やES添削なども可能です。 - 博士情報エンジンwakate
博士やポスドクに特化したキャリア支援サイトです。
博士のキャリアをテーマとしたイベントやセミナーも数多く開催されており、就活のつかみを知るためにぜひ参加をおすすめします。
Xでは、博士採用情報として、博士向け企業のエントリー情報をお知らせしてくれます。 - tayo
簡単に自分のポートフォリオを作成することができます。
開催されているイベントも個性があり、いつか起業を考えている人にはおすすめできるコンテンツが豊富です。 - LabBase
研究内容やスキルを登録することで、スカウトやイベント等を通して企業と繋がれる就活サービスです。
僕自身はあまり有効に使うことができませんでしたが、機電・情報系の学生はぜひ押さえておきたいところです。 - ONE CARRER・unistyle・就活会議
いずれもESの参考のために登録しました。
Phase2:選考準備・書類準備
いよいよ本格的な準備へと進んでいきます。
研究概要の作成
研究概要の作成には、本気で取り組みましょう。
特に博士課程の早期選考では、研究概要のクオリティが結果を左右すると言っても過言ではありません。
いろんなフォーマットがあるかと思いますし、僕は自分の作成したものが正解だとは思っていませんが、作成時に意識したポイントを箇条書きでまとめておきます。
- Wordで作成する人が多いと聞きましたが、僕はPowerPointで作成しました。文章よりも図の訴求力を重視して、より図の調整がしやすいツールを使いたかったというのが大きな理由です。
- 学振と同じく、最初の1ページ・最初の1セクションで勝負が決まります。ここで目に留まらなければ、その先は読んでもらえません。
- 1ページ目の前半には、研究背景と概要をシンプルかつ明快に。ここまでは専門外の人も含めて全員目を通してくれる想定で書きます。ここでしくじると、人事は興味を持ってくれないと思いましょう。
- 研究の意義は、実社会とのつながりを意識して書くことが重要です。社会実装や還元への視点を盛り込むことが、アカデミア向けとの大きな違いになります。
- 1ページ目の後半からは、自身の専門性や研究の独自性を絡めながら、研究成果をアピールしていきます。ここは相手も研究のプロ。ロジックがしっかりしていれば、必ず理解してもらえます。ただ、専門用語の使用は最小限に抑え、補足も入れると親切です(少なくとも学振と同程度の配慮が必要)。
- figのクオリティはとことん追求しましょう。1ページ目の前半で最初に載せるGraphic Abstractは、その後の理解度を決定します。学部生向けのポスターを作る気持ちで、わかりやすさを最優先に。カラーで印刷・閲覧されることが多いので、配色も気にしすぎなくて大丈夫です。
- 最後のセクションは、今後の展望に触れるのが無難です。企業の研究開発では、より短いスパンで成果を出すことが求められるため、次に何をするかを見据える姿勢は評価されやすいと思っています。研究の新規性や独自性を補強する内容でもよいでしょう。
学振と同じで、必ず第三者添削してもらうようにしましょう。

僕は前にいたラボで、志望業界に進んだ先輩・同期・後輩に見てもらいました。
また、有料の添削サービスもおすすめです。
博士就活の情報発信のパイオニアであるtabeさんが、添削のサービスを実施されていたので、僕も利用させていただきました。
ポートフォリオの作成
就活支援サイトの中には、基本的なプロフィールに加え、研究内容・所属学会・自己PRなどを掲載できるポートフォリオ機能を備えているものがあります。
生命科学系では必須とまでは言えませんが、情報系では自分の成果物を整理・共有する手段として活用されることが多い印象です。
実際、ポートフォリオを見た企業から直接スカウトが届くケースも少なくありません。
ESや履歴書にリンクを貼ることも可能ですし、貼らなくても企業の人事が確認していることもあるようです。
人事に対してプラスαの材料を提示できるという点で、ポートフォリオは充実させておくと良いアピールになります。
前述していますが、就活支援サービスtayoでは、ポートフォリオのフォーマットが整っているので、特におすすめです。
Phase3:エントリー・選考序盤
企業へのエントリー・企業説明会
当時の僕は、どのくらいの企業にエントリーすればいいのかさえ分からず、不安な気持ちで手探りの状態でした。
しかし実際に就活を経験して感じたのは、業界研究・企業研究をしっかり行っていれば、エントリーの数はそれほど多くならないということです。
僕は少しでも興味を持った企業30社ほどでマイページを作り、そのうちESを提出したのは15社(うち数社は使い回し)でしたが、正直15社は多すぎたと感じています。
業界研究・企業研究をもう少し深くやれていれば、10社以下に絞れたはずだと振り返ります。
ただ、何社が正解ということはなく、自分のキャパと都度相談したり、志望度で優先順位をつけたりすることが大切です。
企業説明会については、個人的にはあまり有意義だったとは言えないことが多かったです。(ただし、出なくてよかったかは結果論なので一概には言えません。)
十分な企業分析ができていれば、説明会で目新しい情報が得られることは少ないと思います。
とはいえ、答え合わせの機会として参加したり、実際に質問して価値観のすり合わせを行う時間として考えれば、有効に活用できる場ではあります。
自己PR・志望動機のブラッシュアップ
大事なことは、ここまでの自己分析・企業研究です。どのくらい理解を深められたのかですべてが決まります。
「その企業にしかない優位性・独自性と、自分のストロングポイントがかけ算できると、こんな未来が期待できる」という軸が1つ2つ決まってしまえば、あとは設問ごとに一貫性をもって答えていくだけで、十分に優れた回答になると思います。
最後の細かいブラッシュアップは、ChatGPTのような生成AIに任せてしまえば、驚くほどスマートに整えてくれます。
生成AIが身近にあるこの時代、表現力や国語力で大きな差がつかなくなったのは、個人的にはありがたかったです。
SPIなどのWebテスト対策
SPIの青本だけ買って、気分転換に遊び感覚で解いていました。いろんなテストがありますが、大抵同じような問題なので、テスト別対策はまったく不要です。
推論系はコツを知ってるだけで対応が早くなるので、触れておいてよかったですが、それ以外は安心材料くらいの意味しかなかったかなと思っています。
選択式の問題はなんとなくで正解できることも多いですし、少し考えても解けない一部の問題は本番では捨てることになります。
正直、SPIに時間をかけるよりも、自己分析や企業研究を深めるほうが大事だと思います。
Phase4:最終選考・内定獲得
オンライン面接・対面面接・最終面接
博士早期選考では、技術面接と最終面接を含む、2〜3回の面接を経るのが一般的です。
面接対策といえば、まず想定質問への回答準備ですが、これもやはり自己分析と企業研究の深さがカギになります。
僕の解釈では、企業の面接官は「加点方式」ではなく「減点方式」で評価しており、そこに第一印象や熱意などで加点されていく構造だと感じました。
企業にとっては、優秀な人材を逃すよりも、合わない人材を採用してしまうことのほうがリスクだからです。
そのため面接では、研究内容・課題解決力・チームワーク・将来像など、致命的な落とし穴がないかを多角的にチェックされているように思います。
そのためまずは、どんな切り口の質問にも質実剛健な回答ができるよう準備しておきたいところです。
というのも、これは僕自身、かなり反省が残った部分でした。1回目の面接では耳障りの良い言葉でなんとかごまかせても、最終面接が近づくほどボロが出て落ちるというパターンが多かったからです。
特に技術面接では、研究内容を深掘りが大半だと思い込み、研究内容に自信がなかったこともあって、そこばかりに時間を割いていました。その結果、研究姿勢やチーム内での役割、困難への向き合い方といった、人となりに関する質問には、準備不足が露呈しました。
たとえば、
- 「チームで研究した経験はあるか?」
- 「どんな役割を意識していたか?」
- 「一番大変だったことは?」
- 「それをどう乗り越えたか?」
といった問いに、場当たり的で要領を得ない返答しかできず、印象も弱くなってしまいました。
また、肝心の研究内容についても分野外からの鋭い質問は想定が難しく、時間をかけた割には対策があまり活きなかった印象です。
面接は得意だと根拠もなく思い込んでいた分、余計に手応えのないまま終わってしまい、自分の弱点を直視せずに臨んだ結果、きちんと相応の結果が返ってきたなと、後から痛感しました。
本番では、簡潔に、明快に話すことを常に意識しましょう。
そして、面接を通して自分を立体的に伝える準備を、丁寧に積み重ねていくことが大切だと思います。
まとめ:博士の就活も、準備がものを言う
この記事では、博士課程ならではの就活の流れや、準備のポイントについて紹介してきました。
情報が少なく、不安になりやすい博士就活ですが、しっかり準備すれば、結果が大きく変わる場面は多くあるはずです。
自分の強みや進路についてじっくり考える最後のチャンスだからこそ、自己分析や企業研究にも力を入れてみると、結果的にいい就活につながるのではないでしょうか。
正直なところ、僕自身は、博士の就活を短期間で一気に終わらせるという風潮には違和感がありました。
博士は本業である研究が忙しいからこそ、長期的な視点でじっくり取り組む就活のあり方も自然だと思います。

偉そうに話していますが、人に自慢できるほど華々しい戦績はまるで収められませんでした。
それでも、納得のいく就活はできたと思っています。
就活が佳境に入ると、研究との両立で本当に忙しくなります。
だからこそ、自分のペースを見失わず、自身のメンタルケアも大切に。メンタルも就活パフォーマンスを支える土台としてめちゃくちゃ大事ですので。
丁寧な準備を重ねて、自分に合ったキャリアをつかみにいきましょう。
では。