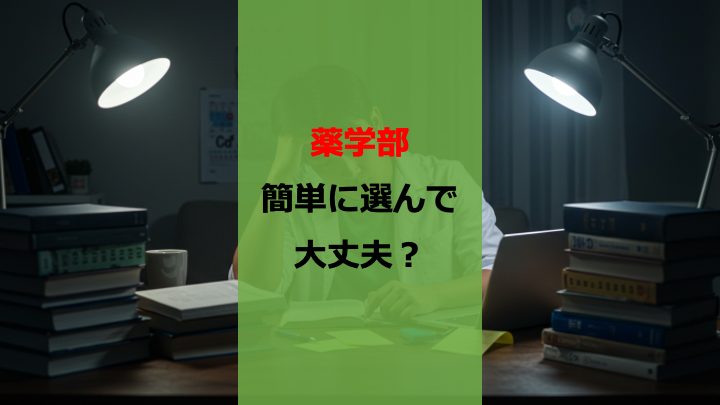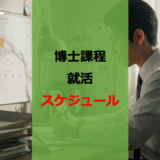こんにちは。ぱにです。

医学系の研究室で博士号取得を目指しています。
薬学部への進路を考えている高校生に向けて、この記事ではあえて薬学部の現実をお伝えします。
- 人の健康や医療に関わる仕事がしたい
- 医療系なら将来なくならないから困らなさそう
- 薬剤師って医療職の中では楽に稼げそう
そんなふうに考えて、薬学部を目指す高校生は少なくないはずです。
僕自身、大学院までの6年間を国立の薬学部で過ごし、たくさんの薬学生と出会ってきましたが、正直、なんとなくで入ってしまうと、幸せになれる学部だとは言えません。
もちろん、明確な意思と目的を持ち、勉学に励むことができれば、薬学部は人生にとってかけがえのない経験を与えてくれる場所でもあります。
この記事を通じて、あなたが薬学部に抱いているイメージが、現実とどれだけ一致しているのかを、今一度確かめてみてください。
進路選びで後悔しないためにも、ぜひ最後まで読んでいただければと思います。
以下の記事も参考にしてみてください↓
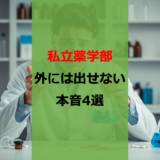 【実際に聞いてみた】私立薬学部に進んで後悔した4つの理由【卒後の本音】
【実際に聞いてみた】私立薬学部に進んで後悔した4つの理由【卒後の本音】
ややこしさの元凶:4年制と6年制
薬学部には、大きく2つの学科があります。
- 薬学科(6年制):薬剤師国家試験の受験資格が得られる。薬剤師を目指す人は必ずこちら。
- 薬科学科(4年制):創薬・薬品開発などの研究者を育てるコース。大学院へ進学する人が多い。
つまり、薬を扱う側(調剤・処方)と薬をつくる側(研究・開発)とが、薬学部というひとつの枠に一緒くたにまとめられているのが、薬学部のややこしさの根本です。

かつてはこの区別がなく、薬学部を4年で卒業すれば全員が薬剤師国家試験を受けることができました。
現在の制度では、薬剤師を目指す人は6年制を選ばないと国家試験の受験資格すら得られません。
そのため、高校生のうちに、薬学の中でも医療の現場で薬を扱いたいのか、薬の研究開発に携わりたいのか、ある程度は考えておくことべきだと思います。
もっとも、迷っている人は薬学科(6年制)を選んでおけば、薬剤師にも研究者にもどちらにもなれる余地があります。
ただし、6年制で研究の道に進もうとすると、実務実習や国家試験対策に追われてしまい、研究に十分な時間を割けないという問題が出てきます。
4年制から大学院へと進む進路のほうが、研究に集中しやすい環境が整っており、実績を積むうえでは有利であることは間違いありません。
また、研究者志望であっても、6年制であれば国家試験を受けることになるケースが多く、将来使うか分からない薬剤師免許のためにモチベーションを維持する工夫が求められる点も知っておいてほしいところです。
進学先を選ぶ際は、薬剤師になりたいから薬学部、というだけでなく、4年制と6年制の違いと、それぞれの進路に合った選び方をぜひ意識してみてください。
薬学部の学費の現実:国立 vs 私立
薬や医療は、誰にとっても身近で、ありがたみを感じやすい分野です。
そのためか、薬学部は高校生にとって人気の高い進路のひとつとなっています。
実際、同じ大学内で学部を比較しても、薬学部は倍率が高く、偏差値も高めに設定されていることが多く見られます。
なかでも国立大学の薬学部は定員が少なく、非常に狭き門です。
旧帝大をはじめとする国立薬学部に合格するには、相当な学力と対策が求められます。

あくまで偏った個人的な印象ではありますが、僕が通った国立の薬学部には、実家からの経済的支援が潤沢な一部の医学部生とは異なり、雑草魂を持った、真面目で勉強熱心な学生が多いように感じました。
一方、私立大学の薬学部は比較的門戸が広く、受験のハードルはやや下がる傾向にあります。
しかし、そこで大きな壁となるのが、6年間にかかる学費の高さです。
たとえば、学費の総額は以下の通りです:
- 国立大学:約350万〜400万円
- 私立大学:約1000万〜1300万円以上
中には、6年間で1500万円を超える私立薬学部も存在し、これは文系学部の2〜3倍、大学によっては私立医学部に迫る金額です。
さらに薬学部では、実習や進級判定の厳しさ、国家試験の難易度などから、留年が決して珍しくありません。
こうした事情を踏まえると、私立薬学部は家計にとって非常に大きな負担となる進路であることがわかります。
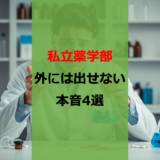 【実際に聞いてみた】私立薬学部に進んで後悔した4つの理由【卒後の本音】
【実際に聞いてみた】私立薬学部に進んで後悔した4つの理由【卒後の本音】
大学入っても勉強三昧
薬学部では、その専門性の高さゆえに、多くの必修授業を受講することが求められます。
そのため、本来なら大学生活の醍醐味でもある自由な時間割の編成も、薬学部では選択の自由度が極めて低く、思っていたほど自由を感じられないというのが実情です。
学ぶ内容は非常に幅広く、化学・生物学に加え、物理学・統計学・薬理学・衛生学など、薬に関わるあらゆる分野を網羅的に学ぶ必要があります。
もちろん、苦手な分野があると容赦なく単位を落とすことになるため、どの分野にも対応できるバランスの取れた理解力が求められます。
これは想像以上にハードで、テスト期間になると、まるで高校生に戻ったかのように大量の教科書やプリントに囲まれて猛勉強する日々が続きます。
2〜3年次には実験実習が本格的にスタートし、実習によっては夜遅くまで大学に残って作業をすることもあります。
本業とはいえ、学業が生活をどんどん圧迫するようになるため、想像していた大学生活とのギャップを感じる人も少なくないかもしれません。
4年次になると、研究室に配属され、自分の裁量で研究を進める日々が始まります。
4年制の学生が大学院に進学すれば、その後も含めて3年間、研究漬けの生活が続きます。
一方、6年制の薬学科では、研究活動に加えて、OSCE(客観的臨床能力試験)という実技試験に合格しなくてはなりません。
その後も、薬剤師国家試験に向けて、半年間の実務実習、卒業試験、そして国家試験と、怒涛の試験ラッシュが待ち受けています。
そして、2月に行われる国家試験に合格してようやくゴールとなるわけです。
このように、薬学部は入るのも難しいが、出ていくのも相当大変な学部です。
「勉強が苦手」「自由な大学生活を送りたい」と考えている人にとっては、なかなか覚悟がいる道かもしれません。
薬剤師は勝ち組の職業なのか?
これだけ苦労して手に入れた薬剤師免許。これで将来は安泰だ、と思いたいところですが、現実はそこまで甘くないかもしれません。
まずは、薬学部出身者が主に進む職種の、30歳時点の平均年収(概算)を見てみましょう。
※地域・企業規模・経験年数により差があります。あくまで目安です。
- 病院薬剤師:約450万円〜550万円
- 調剤薬局の薬剤師:約500万円〜600万円
- ドラッグストアの薬剤師:約500万円〜700万円
- 公務員薬剤師:約500万円〜600万円
- 製薬企業(研究職):約600万円〜800万円
- 製薬企業(開発職・MRなど):約550万円〜750万円
こうして見ると、薬剤師免許があるからといって、高年収が保証されるわけではないことがわかります。
特に意外なのは、専門性を求められる病院薬剤師よりも、ドラッグストア勤務の方が収入が高くなる傾向があることです。
実際、時給2000〜3000円超のバイト求人も多く、魅力的に映るかもしれません。
しかしその一方で、昇進・昇給の伸びしろが小さく、専門性が積みにくいという課題もあります。これは調剤薬局でも同様です。
さらに近年では、薬剤師がAIに代替されるリスクも叫ばれています。
すでに調剤業務の自動化や監査システムが進み、「薬を渡すだけ」の仕事は機械に取って代わられる未来が現実味を帯びています。
それでも薬学部の人気は根強く、私立大学の新設も相次ぎ、薬剤師の数は年々増加しています。
近い将来、薬剤師の供給過多による就職難も現実味を帯びてくるかもしれません。
加えて、医療費抑制の流れも逆風となっています。
医師ですら診療報酬の引き下げに直面しているなか、薬局も調剤報酬の度重なる引き下げにより、業界全体の収益性が厳しくなっているのが実情です。
下手な医学部よりも入試難易度が高いと言われるくらい、国立大学の薬学部に合格する学生は、本当に優秀です。
それほどの学生が、処方箋を右から左に流すだけの仕事に収まってしまうのは、実にもったいないと言わざるを得ません。
かといって、私立薬学部の場合、6年間で1000万円以上かかった学費という名の投資を、薬剤師として回収するのは容易ではないでしょう。
一方で、製薬企業や研究機関などに進めば、専門性を活かしてキャリアアップや高収入を目指す道もあります。
ただしその道も平坦ではなく、修士・博士課程への進学、研究実績、語学力など、高いハードルが立ちはだかります。
それでも薬学部には価値がある

手厳しいことも書きましたが、僕自身は薬学部へ進んだことを誇りに思っています。
たしかに薬剤師という職業には課題もありますが、薬学部で得られる価値はそれ以上に大きなものです。
薬学はそもそも、化学・生物・物理など複数の学問が融合した学問領域であり、幅広い分野の知識を体系的に学べる点が大きな特長です。
その知識は、家族の体調管理や市販薬の選び方、感染症予防など、日常生活にも直結して役立ちます。
さらに、医療制度や社会薬学を通じて、現代医療の課題を理解できる点も薬学部ならではの学びです。
製薬企業や研究職を目指す際にも、薬学部で培った専門性は大きな強みになります。
そしてやはり、国家資格である以上、薬剤師免許は一生ものの経歴です。就職や再就職に困ることはほとんどありません。
特に女性にとっては、出産や育児によるブランク後も復職しやすく、産休・育休後の復帰率が高い点も魅力です。
どのような進路を進むとしても、人の健康や命に関わる知識を持つことには大きな価値があります。
薬学部は、単に資格を取る場所ではなく、社会に貢献する力を育てる学びの場なのです。
まとめ:目的を持って、薬学部を目指そう
この記事では、薬学部が抱えるリアルな課題や卒業生のキャリアの実態など、できるだけ包み隠さずお伝えしてきました。
どの学部にも言えることですが、特に薬学部は「なんとなく」で選ぶには厳しい場所です。
もちろん、薬を通じて多くの人の命を救いたいという志はとても尊いものです。
だからこそ、自分はどのように薬に関わっていきたいのか、具体的なビジョンを持つことが大切です。
興味があるなら、オープンキャンパスに参加したり、実際に通っている先輩の話を聞いたりして、自分の目で確かめてみることをおすすめします。
将来を左右する選択だからこそ、他人任せではなく、自分の頭でしっかり判断して決めてほしいと思います。
後悔のない進路選びになりますように。
では。