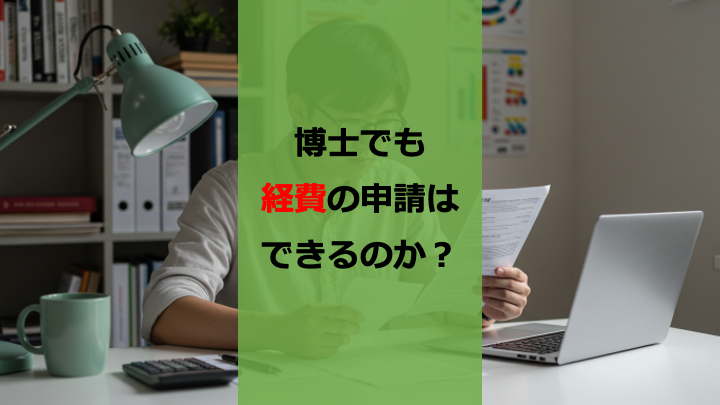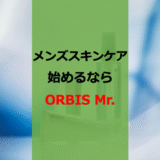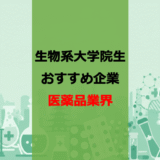こんにちは。ぱにです。

医学系の研究室で博士号取得を目指しています。
この記事では、少しでも金銭的な負担を減らしたいと考えている博士課程の学生・大学院生に向けて、経費の申請について正しい情報をお伝えします。
以前の記事でも解説した通り、博士課程へのわずかな経済支援に対して、意外と大きな税負担が課されるケースがあります。
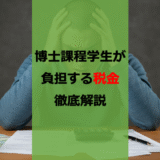 【令和7年度税制改正反映】博士課程で収入を得たらかかる税金と社会保険まとめ【徹底解説】
【令和7年度税制改正反映】博士課程で収入を得たらかかる税金と社会保険まとめ【徹底解説】
この事実を知ると、どうにかして支払う税金を減らせないか、と考えるのが自然な流れでしょう。
そこで今回は、特に負担の重い雑所得収入に適用できる節税の仕組みについて、わかりやすく解説します。
ぜひ最後まで読んでいただき、お金の知識を身につける一助にしてもらえたら嬉しいです。
本記事は一般的な情報提供を目的としています。
具体的な税務判断については、税理士または税務署へご相談ください。
雑所得は経費控除できる
博士課程の学生が受け取る経済支援には、主に給与所得と雑所得の2つの所得区分があります。
- 給与所得になる例
TA(ティーチング・アシスタント)・RA(リサーチ・アシスタント、契約形態による)・日本学術振興会の特別研究員(DC)など。 - 雑所得になる例
次世代研究者挑戦的研究プログラム・次世代AI人材育成プログラム・科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ・その他大学独自のフェローシップなど。
このうち、経費の申請ができる可能性があるのは、雑所得に分類される収入です。
雑所得とは、給与所得や事業所得など他の所得区分に当てはまらない所得を指します。
原則として、その所得を得るために直接必要だった経費を差し引いた金額が課税対象となります。
博士課程の学生が雑所得に分類される経済支援を受けている場合も例外ではなく、研究に必要だった支出を必要経費として申告できる可能性があります。
もちろん、何が経費として認められるかは税務署の判断次第ですが、正しく申告することが節税の第一歩になります。
経費申請できる具体的な費用例
以下は、複数の資料や個人的経験に基づいて整理した内容です。
税務上の判断はあくまで個別の状況によって異なります。経費計上の最終判断は各自の責任で行ってください。
通学・進学に伴う費用
- 学費(大学の授業料)
- 通学のための交通費・定期代
研究活動に直接必要な費用
- 学会年会費・参加費(参加登録料、発表料など)
- 学会参加のための旅費交通費(航空券、宿泊費、現地交通費など)
- 研究活動に必要な書籍・論文の購入費用(専門書、論文課金など)
- 論文投稿料(APC:Article Processing Charge)
機材・ソフトウェア関連
- 研究用のパソコン本体(ただし私的利用と併用の場合は合理的な按分が必要)
- 研究に必要なソフトウェアの購入・ライセンス費用(統計解析ソフト・文献管理ソフトなど)
研究能力向上・教育関連
- 研究に直接関連する外部セミナー・講習会の参加費用

僕は主に、大学の授業料と定期代・学会の年会費を経費として申請しています。
節税効果をざっくり計算
以下は、博士課程の経済支援として雑所得200万円を受け取った場合の試算です。
◆仮定のケース:
- 年間の雑所得:200万円
- 経費として申告できた金額:50万円
- 所得控除:基礎控除(所得税:88万円、住民税:43万円)のみと仮定
- 所得税率:5%、住民税:10%(均等割のみの概算)
| 経費なし | 経費あり(50万円) | |
|---|---|---|
| 合計所得金額 | 200万円 | 200万円 − 50万円 = 150万円 |
| 所得税 | 56,000円 | 31,000円 |
| 住民税 | 157,000円 | 107,000円 |
| 合計 | 213,000円 | 138,000円 |
| 節税額 | — | 75,000円 |

控除を考慮しなければ、「節税額 ≒ 経費 × 15%」と見積もることもできそうです。
加えて、雑所得から経費を引いたあとの金額は、国民健康保険料の算定基準にもなります。
今回の例(経費あり150万円/なし200万円)では、経費の申告により年間3〜4万円程度の保険料軽減が期待できます(自治体によって異なります)。
まとめると、経費を申請することによって、合計で10万円前後の負担軽減になる可能性があります。
詳しい計算方法はこちらの記事で徹底解説しています。
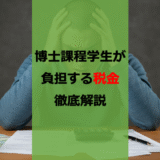 【令和7年度税制改正反映】博士課程で収入を得たらかかる税金と社会保険まとめ【徹底解説】
【令和7年度税制改正反映】博士課程で収入を得たらかかる税金と社会保険まとめ【徹底解説】
経費申請のポイントと注意:リスク管理
確定申告時にまとめて経費を申請
経費は年1回、確定申告でまとめて申請します。
e-taxでは、雑所得(その他)の入力時に、収入金額と必要経費それぞれの欄が出てくるので、あらかじめ計算した金額を入力するだけで完了します。
領収書は必ず保管
経費とするには、支払いを証明する書類(領収書・明細など)の保存が不可欠です。
メール明細やクレカの利用履歴でも代替できる場合がありますが、備えとして可能な限り紙やPDFで保存・整理しておきましょう。
私用との併用はおおよそで按分計算が必要
PCや定期代など研究と私用を兼ねる支出は、合理的な利用割合(例:研究7割、私用3割)を決めてその分だけ経費としましょう。
細かくなくても、説明がつけばOKです。
説明できることが最重要
按分計算の話も然り、経費の内容は税務署から聞かれる可能性があります。
なぜ研究に必要だったかを自分の言葉で説明できれば、十分対応できます。
まとめ:博士課程で経費申請はできる
この記事では、雑所得に該当する収入に対する経費申請の基本について解説しました。
学会費や書籍代、交通費など、研究に必要な支出は経費として申告できる可能性がありますが、どの支出が経費として通るのか、自分でよく判断することが大切です。
お金に関する知識は、それ自体が「お金を守る力」になります。
これからも一緒に学びながら、僕自身もお金のやりくり、頑張っていきます。
では。