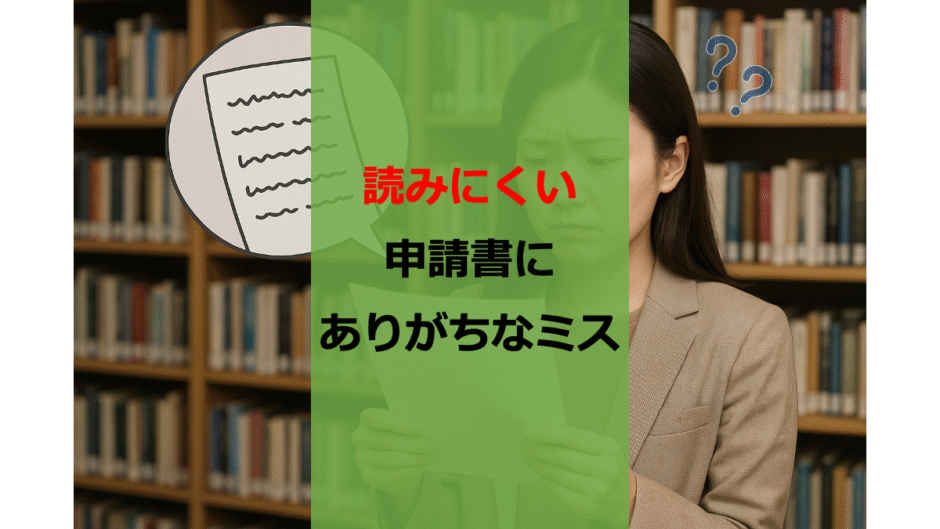こんにちは。ぱにです。

医学系の研究室で博士号取得を目指しています。
この記事では、申請書を書く上で注意しておきたいことのうち、読まれることに対する意識を深掘りして考えていきます。
- 「内容はいいんだけどイマイチ頭に入ってこないな」
- 「結局一番伝えたいメッセージってどれ?」
申請書を書いていてこんなアドバイスをもらった人も少なくないのではと思います。
これらに対する回答を用意するのって、アドバイスが曖昧だからこそ難しく、研究とは違う頭を使わなきゃいけなくて大変なんですよね。
僕にとっても申請書を書くことは面倒で大変ですし、それになんとなく本質ではない気がして億劫な気持ちになります。
この記事を読むことで、申請書を修正する際に体系的に自己添削できるようになるかもしれません。
実際に自分で申請書を書く際に、是非役立てていただければと思います。
大前提は内容が良い申請書であること
いきなり出鼻を挫くようですが、申請書で重要なことは第一に内容の良さです。
内容がずば抜けてよければ、これから書く内容は”小手先の技術”と一蹴されてしまうでしょう。
そのくらい、申請書の中身については最大限の時間を費やして良いものに仕上げるべきです。
つまるところ、「読みやすい」申請書を書く技術をこの記事で学ぶ最大のメリットは、
申請書の中身をブラッシュアップする時間を少しでも増やすことにあると思っています。
本質じゃないからこそ、そんな枝葉末節に振り回されないように、先手を打って一緒に考えてみましょう。
「読みにくい」「読みづらい」は大きく3つに分類できる
では、文章を作成してなんだか内容が頭に入ってこないと感じたら、何をチェックすればいいのでしょうか。
文章の読みにくさをもたらす原因は大きく3つあります。
それは、①「可読性の低下」②「視認性の低下」③「判読性の低下」の3つです。
①可読性(readability)
可読性とは、文字や文章が物理的に読みやすいかの指標のことです。
たとえば、読点がほとんどなくて読みにくい場合は、「可読性が低い」と表現できます。
新聞などの活字媒体では、漢字3割・ひらがな7割の原則があると言われており、この適切な比率によって「可読性が高まっている」といえるでしょう。
申請書でよくある可読性低下のミスは、行間と余白です。
限られたスペースの中に必死に言葉を詰め込むあまり、文字でギュウギュウとなった申請書にならないように見返してみましょう。

入り切らないという場合は、そもそも表現が冗長の可能性がありますね。
②視認性(visibility)
視認性とは、目で瞬間的に見たときに正確に文字として認識できるかの指標のことです。
たとえば、フォントを多用した結果読みにくくなっている場合は、「視認性が低い」と表現できます。
申請書で気をつけたい視認性のポイントは、ボールド(太字)の使い所です。
ボールドを上手く使うことで、申請書の中でも特に重要なメッセージを浮かび上がらせることができるため、強力なツールであることは疑う余地もありません。
しかし、ボールドを使うことで文字の視認性が下がることは知っておくといいと思います。
③判読性(legibility)
判読性とは、誤読をさせずに文章の意味が伝わるかの指標のことです。
たとえば、0(ゼロ)とO(オー)とが混同しやすいことを「判読性が低い」と表現します。
申請書で判読性が低下する最大の原因は、専門用語の多用です。
審査をする先生方の専門分野と、申請者の専門分野とが必ずしも合致する訳ではありません。
前提知識のない先生方に専門用語を乱発すると、読み手は必要以上に推測しながら読むことになり、その結果文章の理解度が下がってしまうため注意しましょう。

専門用語を専門用語で解説していた、なんてこともしばしばですよね。。。
最も良いブラッシュアップの方法は専門外の人に何度も読んでもらうこと
ここまで読んでみてどんな感想を持ったでしょうか?
当たり前のことしか書いてないと思った方も少なくないのかなと思います。
でも案外、読みやすい文章を書くことができる人であっても、申請書を書くことに集中してしまうと、この当たり前が守れなくなっているんですよね。
自分ではどうしようも打開できないこんなときは、自分の専門分野外の人に読んでもらうのがおすすめです。
自分の専門に近い分野では無意識に当たり前としていたパッとしない表現やフォーマットを、ズバッと指摘されて一気に読みやすくなる可能性がグッと高まります。

別の研究室の同期や先輩だけでなく、家族や恋人にも見てもらった経験があります笑
読みやすさという点においては、添削者にそんなに気合はいらないかなとも思うので、是非いろんな人に声をかけてみてください。
まとめ:「読みにくさ」を因数分解して手早くセルフチェックできるようになろう
ここまでお伝えした「可読性」「視認性」「判読性」の3つのポイントを押さえることで、「読みにくい」からはかなり脱却できたのではないでしょうか。
最初に内容が第一とは言いましたが、その内容に優劣がつかなかったときに意外とこういう「読みやすさ」が審査員の先生の心証を左右していたりしますので侮れないですね。
「読みやすい」申請書が書けるようになってきたうえで、さらに+αで僕自身が気をつけていることは、以下の記事でまとまっています。
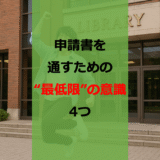 【通ってしまえば】申請書をギリギリ通してきた僕が最低限意識していること4つ【こっちのもの】
【通ってしまえば】申請書をギリギリ通してきた僕が最低限意識していること4つ【こっちのもの】
少しでも多くの申請書が通るように、引き続き頑張っていきましょう!
では。