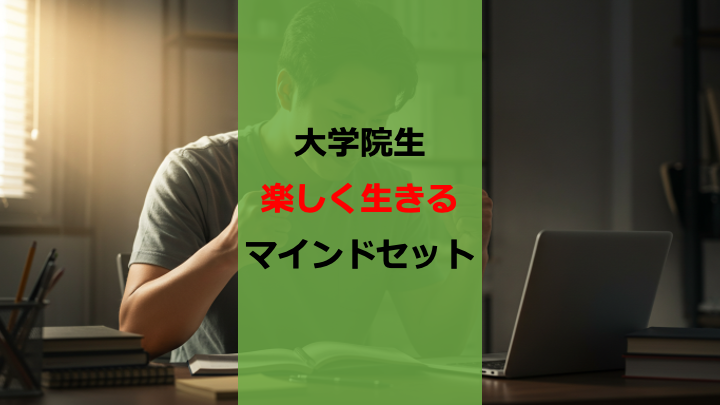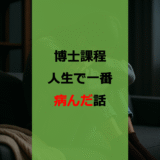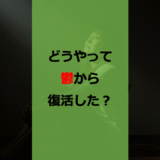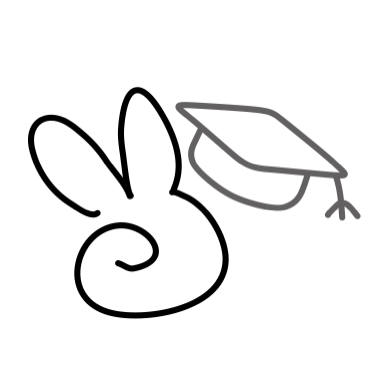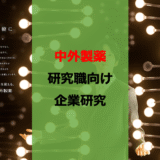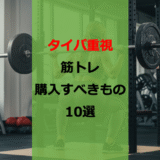こんにちは。ぱにです。

医学系の研究室で博士号取得を目指しています。
この記事では、大学での研究生活につらさを感じている大学院生・大学生に向けて、現役の博士課程の僕が実践している楽しく生きるためのマインドを紹介します。
- 研究に追われる毎日がしんどい。。
- 将来、このままで本当に大丈夫なんだろうか。。
そんな不安や悩みを抱えているのは、あなただけではありません。むしろ、同じような思いをしている人は世の中にたくさんいます。
Fラン大学院生である僕自身も、約7年にもおよぶ研究生活のなかで何度も挫折し、もうダメだと弱気になったことは一度や二度ではありません。
それでも今はなんとか、自分を励ましながら研究と向き合い、ストレスをため込まないように日々を過ごせているつもりです。
きっと、今日よりほんの少しだけ気持ちが楽になるヒントが見つかるはず。
ぜひ、最後まで読んでみてください。
僕が博士課程で病んでしまった一部始終はこちらから↓
自分がご機嫌でいることを最優先する
もし今、しんどいなと感じているなら、まずは自分の心を満たすことを優先してみてください。
心に余裕がないまま誰かのために行動しても、多くの場合、それは自分にとって大きな負担になってしまいます。見返りを求めたくなってしまうこともあるかもしれません。
でも、自分の心が満たされていれば、そこから溢れた分というのは、誰かに気前よく分け与えることができ、お互いがよりハッピーになることができます。
多少のわがままであっても、まずは自分の心を満たすべきなのかもしれない。このことに僕が気がつけたのは、就職活動を通してでした。
「何をやるか(=What)」が満たされれば幸せになれる。そう思って、やりたいことをあれこれ考えたりもしましたが、なかなかしっくりくる答えは見つかりませんでした。

むしろ、たとえ資産を10億円築けたとしても、心が満たされるとは限らないのかもしれない、と感じるようになったのです。
でも、裏を返せばこれは、どれだけ大変な研究に向き合っていたとしても、心の持ちよう次第で楽しく生きることはできるという気づきにもつながりました。
だからこそ、「何をするか」よりも、「どう在りたいか(=How)」を大切にすることが大事だと感じています。
自分がどんな状態なら楽しくリラックスできるのか。自分の機嫌は自分で取るという習慣を持てると、しんどい日々も少しずつ変わっていくはずです。
遊びなくして幸せな人生なし
ただ生きているだけでも、研究に仕事に人間関係にと、しんどいことはたくさんあります。
そうした「しんどさ」と正面から真面目に向き合い続けていると、どう頑張っても心も身体もすり減ってしまいます。
そこで大切なのが、日常の中に遊びを取り入れることです。
といっても、夜の街へ繰り出そうとか言っているわけではありません。
自分が楽しくて、リラックスできて、ストレス発散になるような活動であれば、なんでもいいんです。
趣味と呼べるほど立派なものでなくても構いません。
たとえば、友人と食事に行く。恋人と散歩する。カフェで一人ゆっくり過ごす。そういった小さなことで十分です。

現在の僕にとって、一番の楽しみな予定はダイビングです。海でぷかぷか潜っているだけで、いろいろとどうでもよくなって、とても心地いいんです笑。
もし可能ならば、家族や研究室とは異なるコミュニティで活動するとより良いと思います。
自身の価値観の偏りに気がつき、いろいろなことを学べるきっかけになります。
大学院生にありがちなのが、研究や仕事が最優先で遊ぶのは甘えだと思い込んでしまうこと。
でも、遊びのない人生は、正直つまらないです。そして、実際に博士課程ではストレスを抱えてうつ状態になってしまう人も多いのが現実です。
時間がないと感じる人は、意識的に遊びの予定をカレンダーに組み込んでみてください。
未来に楽しみがあると、それが日々を乗り越えるエネルギーになりますよ。
できないことはできないと認める
苦手なことを無理してやり続けていると、なかなか結果も出ず、だんだん自分のことが嫌になってしまいます。
自己肯定感が低い人ほど、「できない」と言えずに、無理して頑張ってしまう傾向があります。
できない自分を否定し続けるような思考に陥り、自分の機嫌を自分でコントロールできなくなっていたら、それはもう警報レベルです。

僕の場合がまさにこれでした。しょうもないプライドも邪魔して最悪でした。
とはいえ、大学院生はサラリーマンのようにチームや部署を変えるわけにもいかず、苦手なことと向き合い続けなければならない場面が多いと思います。
そのため、「できない」と自覚したうえで、多少のつらさは覚悟しつつどう工夫して付き合っていくかがとても大切です。
たとえば、自分だけで抱え込まず、得意な人に相談して手を借りるのも立派な選択肢です。
苦手な作業に一人で悩み続けるより、協力を得て前に進んだ方が、結果的に自分の心も軽くなります。
また、毎回しんどさを感じる作業は、ルール化やテンプレート化によって考える負担を減らすだけでも、だいぶ楽になります。
できないことを無理に克服しようとするだけでなく、目的達成のために最適な手段を取るという発想に切り替えること。
これは研究生活に限らず、社会に出てからも非常に大切な考え方なんじゃないかと思います。
定期的に運動する
現代人はどうしても運動不足になりがちです。
特に大学院生のように、毎日パソコンの前で長時間作業する生活では、身体が凝り固まってしまいます。
血の巡りが悪くなると、体が重くなるだけでなく、思考力や集中力も落ちやすくなります。
だからこそ、意識的に体を動かす時間を持つことがとても大切です。
運動には、気分の切り替えにも効果があります。
精神的にしんどいことがあっても、体を動かしている間は、ふと嫌なことを忘れられたり、気持ちがリセットされたりします。
また、運動にはストレスホルモンのコルチゾールを下げ、セロトニンを増やす働きもあり、深い眠りにもつながると言われています。
運動の種類はなんでもOK。水泳でもボルダリングでも、キックボクシングでもヨガでも、自分が楽しいと思えるものがいちばんです。

僕のおすすめは、男女問わず断然筋トレです。ひとりで黙々とできるし、体が変わる実感が自己肯定感にもつながります。
筋トレがいかすばらしいものか、その魅力を全力で語り尽くした記事も書いています↓
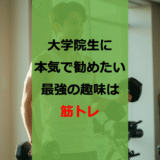 大学院生にこそおすすめしたい最強の趣味は筋トレです【ジム】【脳筋】
大学院生にこそおすすめしたい最強の趣味は筋トレです【ジム】【脳筋】
まとめ:しんどい日々を軽やかにする工夫を
この記事では、つらい研究生活に向き合うためのマインドセットを紹介してきました。
しんどいときは、自分を追い詰めるよりも、まずは自分をご機嫌にしてあげることが何より大切です。
そのために、遊びの時間をつくったり、運動で体を動かしたり、自分に合った形で心を整える工夫が役に立ちます。
できないことを無理に抱え込まず、ときには誰かに頼ったり、うまく仕組みに任せたりしながら、少しずつ前に進めばそれで十分です。
この記事が、読んでくださったあなたの研究生活をほんの少しでも軽くするきっかけになれたら嬉しいです。
では。