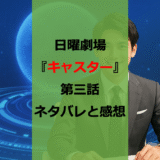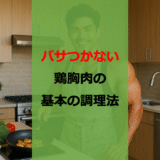こんにちは。ぱにです。

医学系の研究室で博士号取得を目指しています。
この記事では、これから博士課程を目指し、経済的支援を受けたいと考えている方向けに、博士課程の支援制度の現状についてお伝えします。
- 博士学生への支援が拡充したとはいえ、その内容は十分なのだろうか?
- 実際に支援制度でやりくりしている博士学生は、どんな生活をしているのだろうか?
こんな疑問や不安を抱えている修士学生・学部生の方も多いのではないでしょうか。
僕自身、現在進行形で大学より経済的支援を受けている一人として、リアルな実感をもとに支援制度の現状を評価してみたいと思います。
ぜひ最後まで読んで、自分の目指す生活水準と博士支援制度がマッチしているか、擦り合わせる材料にしてみてください。
評価点①:母数拡大を重視した支援により下振れが激減した
かつては博士課程で経済的支援を得るには、学振DCのような狭き門をくぐるしかありませんでした。
学振の合格率は2割前後で、業績を残せるかどうかだけでなく、審査員との相性など運の要素も少なからず絡みます。
その結果、不合格=無収入という“絶望”が待っている状況でした。
しかし近年は、大学独自の給付制度や国の支援拡充によって、「収入なしで博士に進む」という下振れパターンが減りつつあります。
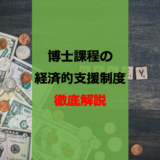 【2025年版】博士課程のための経済的支援制度まとめ【徹底解説】
【2025年版】博士課程のための経済的支援制度まとめ【徹底解説】

僕が所属する地方国立大学では、今年の次世代の倍率は約1.3倍だったそうです。合格率75%。
支援学生の母数を広げる方向へと舵が切られた結果、一部の優秀な学生だけでなく、より多くの学生にチャンスが開かれるようになったことは評価できると思います。
評価点②:最低限の自立した生活が成り立つ
現在の博士支援制度では、たとえば学振DCであれば月額20万円、大学独自の給付型制度でもおおむね月18万円前後の支援が得られます。
この金額があれば、家賃・光熱費・食費といった基本的な生活費は十分にカバーできます。
生活費のためにアルバイトを過剰に掛け持ちする必要がなく、研究という本業に専念できるのは大きな安心材料です。
もちろん余裕があるとは言えませんが、最低限の自立した生活を送るには足る水準だと感じます。
課題点①:就職した同期と比較すると肩身が狭い
最低限の生活水準が約束されているとはいえ、就職した同期と比べると、経済面で肩身の狭さを感じることは少なくありません。
企業勤めの同世代は、ボーナスや各種手当、社会保険や福利厚生によって、生活の余裕や安定感がまるで違います。
旅行やちょっとした外食でも「こっちは毎月ギリギリだな」と、生活の質の差を感じる場面は少なくないと思います。
同期が着々とライフステージを進めていく中、自分は“社会人”と名乗るには経済的に自立しきれず、かといって“学生”というには多大な時間を研究に費やさなくてはならない現実に、悶々とするかもしれません。

中途半端でもどかしい立場であることは間違いありませんね。
課題点②:想像よりも手取りに残らず貯金に回すのは苦しい
前述の通り、博士支援制度では月18万円程度の給付がある場合が多いですが、そこから税金や社会保険料を差し引くと、実質の手取りは15万円前後に落ち着きます。
学生なら何か優遇があるのかと思いきや、実際は意外とお金が引かれる場面が多く、気づかぬうちに可処分所得が削られているという感覚を覚えることもあるでしょう。
最低限の生活水準は確保されてはいますが、貯金や突発的な出費への備えまで手が回らないというのが、実際に支援を受けていて感じる正直なところです。
限られた額面でやりくりしていくためにも、最低限のマネーリテラシーは、博士課程に進むうえでの“必修科目”と言ってもいいかもしれません。
課題点③:ボーナスがない
先ほども少し触れましたが、博士支援制度には、いわゆるボーナスというものが存在しません。(当たり前ですが)
僕も博士課程に進む前は、「ボーナスなんてあくまでオマケで、毎月の家計管理ができていれば問題ない」と思っていました。
けれどいざ無い立場になってみると、研究絡みの旅費交通費の立替や冠婚葬祭などの突発的な出費に備える“臨時収入”の不在が、想像以上に重くのしかかります。
また、年に数回あるまとまったご褒美のような収入がないことは、節目や達成感を得づらく、メンタル的にも地味に堪える部分があると感じています。
課題点④:時間差でかかる年金や税金の圧力が苦しい
生活がやっと回っている中で、住民税や国民年金の請求が時間差で届くと、急にプレッシャーを感じるものです。
どうしても一括納付は現実的でないため、「借金を抱えているような気持ち悪さ」がじわじわ残るのは僕だけではないはず。
猶予申請や分割納付といったお役所手続きも地味にストレスです。
課題点⑤:インフレ対して無力
学振の支給額はここ十数年ほとんど変わっておらず、近年の物価高のなかで実質的な生活水準は目に見えて下がっています。
制度が国主導である以上、インフレに合わせて柔軟に支給額が調整されることはなく、このまましばらくは今の額面が続くと考えるのが自然です。
生活のあらゆるコストがじわじわと上がるなかで、給付額だけが取り残されている現状には、やはり不安を覚えます。
支援額が見直される頃には、多くの学生がすでに疲弊してしまっている。
そんな未来が簡単に想像できてしまうことこそが、最大の問題なのかもしれません。
まとめ:支援は拡充されたが安泰ではない
この記事では、博士課程の経済的支援制度について、実体験をもとにその現状を評価し、課題点を挙げてきました。
決して“優秀”とは言えない僕でも、経済的な不安なく研究に集中できているのは、間違いなく支援制度の拡充のおかげであり、これは心から感謝しています。
とはいえ、「生活は楽になったのか?」と問われれば、そう胸を張って言える状態ではないというのが正直なところです。

「支援がある=生活が安定している」とは限らないのが現状だと思っています。
これから博士課程を目指す方にとって、本記事が忌憚のない意見として、進路を考える一助になれば幸いです。
では。