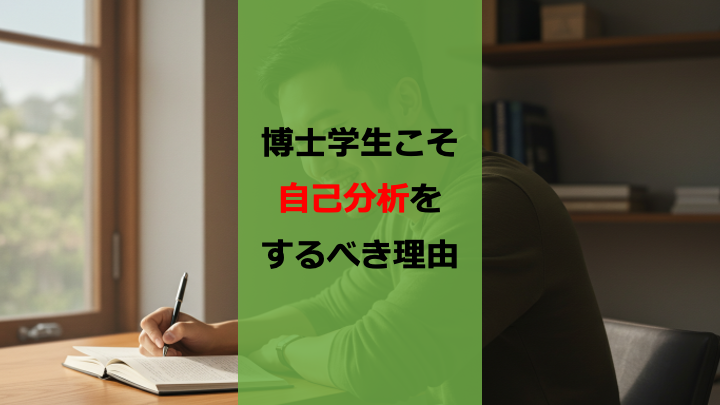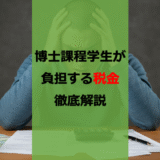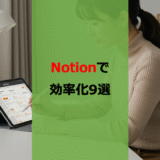こんにちは。ぱにです。

医学系の研究室で博士号取得を目指しています。
この記事では、博士課程に進んだあと、次のキャリアをどう選べばいいのかモヤモヤしている方向けに、自己分析をするべき理由をお伝えしたいと思います。
- 自己分析が大事なのは、あくまで学部生や修士学生が就活するときの話でしょ。
- 博士課程は専門性で勝負すべき。まずは研究を進めることが最優先。
- そもそも自己分析って抽象的すぎて、どこに向かえば正解なの?
これらはすべて、かつて就活前の僕自身が思っていたことです。
でも今、就活を一通り終えた僕がはっきりと言えるのは、博士課程こそできるだけ早く自己分析に向き合うべきだったということです。
確かに、自己分析は就活において最も重要な準備のひとつです。
ですが、就活の準備という意味合い以上に、これからの人生やキャリアをどう築いていくかを考えるうえで、大学院生という時期に自己理解を深めることは、何よりも価値があると感じています。
特に、社会人にも学生にもなりきれない、中途半端な立場である博士学生こそ、自己分析に真剣に取り組むべきだと強く感じました。
修士課程で慌てて人の見様見真似で自己分析をやるよりも、博士課程というモラトリアム期間に自己理解を深められたことは、非常に大きなプラスでした。
自分の原点や価値観を言語化することで、研究の意味も、キャリアの選び方も、きっと変わってくるはずです。
ぜひこの記事が、自分と向き合うきっかけになれば嬉しいです。
※この記事にはアフィリエイトリンクが含まれます。
理由①:自分の人生の羅針盤を手にいれるため
博士課程に進んだというだけで、世間からは明確な目的があって選んだルートだと思われがちです。
しかし実際はどうでしょうか。
「もっと研究がしたい」「博士という箔が欲しい」「まだ社会に出たくない」など、実は漠然とした理由で進んでいる人もいるのではないでしょうか。

僕の進学理由がだいたいこんな感じの勢い任せでした。
個人的にはむしろ、そのちょっとの好奇心や勇気がきっかけで、博士課程にチャレンジする人がどんどん増えていってほしいと思っています。
理系に進んだ人の多くがあまり深く考えずに院進するのと同じように、最初は明確に言葉にできていなくてもいいと思います。
問題は、言語化ができないことそのものではなく、言語化できていないことが危険であることを自覚せず、言葉にできないまま進み続けてしまうこと。
もちろん、博士学生として研究に最大のリソースを投じるべきだと考えるのは至極当然で、これ自体は素晴らしいことです。
しかし博士課程と重なる20代後半というのは、人生において将来の基盤を築く極めて重要な時期でもあります。
研究に没頭し、研究を盾に自分と向き合うことを怠ってしまうと、人生の節目にぶつかったときに、何を大切にすればいいか分からなくなることにつながります。
そこで、自己分析を通して自分の行動の基準を言語化しておくことで、人生の選択に対して自分にとって大事にしたい軸に合うものを選べるようになります。
つまり、自己分析を通じて言語化した価値観が、あらゆる決断の「羅針盤」となるのです。
理由②:博士学生は中途半端な立場にあるため
博士課程の学生は、学生としての高い自由度を持ちながらも、研究室に毎日通い、成果を出すことが求められる立場にあります。
つまり、学生の自由さを備えつつ社会人としての責任も求められる、非常にユニークなポジションにいると言えるわけです。
この立場をネガティブに捉える必要はありません。
むしろ、どちらにも属し切れないからこそ、視野を狭めることなく物事を多角的に考えることができる、人生の中でも極めて貴重なフェーズだといえます。
修士課程では、2〜3年という限られた時間で、研究と就活の両方をこなさなければならず、多くの人が足並みを揃えながら慌ただしく駆け抜けていきます。
社会人になると、目の前の業務や生活の変化に追われ、自分と向き合う余白はぐっと減ってしまいます。
一方、博士課程は時間の自由度も高く、個人の裁量で動ける分、自分の軸で考える機会が格段に増えます。
この自分に使える時間がまだ多いうちに、自分の価値観やキャリア観を整理し、次のスタートラインを自分の手で整地しておくことがとても重要です。
理由③:専門性は還元してこそ意味を持つため
博士課程まで進むと、自分の専門に対して強い愛着と誇りを持つ人が多いと思います。
長い時間をかけて誰よりも深く探究してきたテーマは、まさに唯一無二の専門性だといえるでしょう。
たしかに、アカデミアの道を歩むなら、その深さや独自性は大きな武器になります。
しかし、企業や社会の中で力を発揮したいと考えるなら、専門性の深さだけでなく、それをどう活かし、どう社会に還元できるかという視点も欠かせません。
実際、多くの博士学生が、気づかないうちに専門分野の延長線上でしか将来を描けなくなっているように感じます。
気持ちはよくわかります。自分が情熱を注いできたテーマを簡単に手放すことなんてできませんし、プロとしての自負もあるはずです。
けれど現実には、その専門が企業や社会から求められるかどうかは、時代の流れや企業の事情に大きく左右される側面もあります。
就職活動の場面でも、あまりに専門に固執してしまうと、好きなこと以外には興味がないのかもしれないと思われ、柔軟性に欠ける印象を与えてしまうリスクがあります。
だからこそ重要なのは、専門そのものではなく、研究を通して培った力や特性をどう応用できるかを見極める視点です。
博士課程で得た強みを明らかにし、それをどんな文脈で活かせるかを考えることこそが、博士課程における自己分析の核心だといえます。
それができれば、研究テーマの枠に縛られることなく、専門性を土台にし、武器として、柔軟にキャリアを切り拓いていくことができます。
すなわち自己分析とは、「研究者としての自分」と「社会で生きていく自分」とのあいだにあるアイデンティティのギャップに、前向きに折り合いをつけていくプロセスでもあるのです。
理由④:自分に合う環境を見極めるため
自己分析は、自分の専門や強みを知るだけでなく、自分に合った環境を見極めるためにも不可欠です。
やや就活チックな話にはなりますが、どれだけ専門性が高くても、企業の風土や働き方、ビジョンといった価値観の部分が合っていなければ、本来の力を発揮することは難しくなります。
周囲と価値観がずれたまま働くのは、想像以上にストレスが大きいものです。
どれだけ一生懸命やっても評価されず、思うように活躍できなければ、やっぱり面白くないですよね。
だからこそ大切なのは、「何がやりたいか」だけでなく、仕事を通じて「何を実現したいのか」という視点を持つことです。
目先の職種や業界にとらわれず、どういう人生を送りたいのかというビジョンを描けている人は、環境選びの軸がぶれません。
そしてそのビジョンを描くためには、自分の価値観を深く掘り下げる自己分析が欠かせないのです。
自己分析によって企業とのミスマッチを減らし、自分が本当に力を発揮できる場所を見極める。
それができてはじめて、社会に対して前向きな影響を与えられる人になれるはずです。
おすすめの自己分析の方法
もし具体的に何から始めればいいのかわからないという方には、自己分析に有名な本から入ることをおすすめします。
僕が最もおすすめする本は、『絶対内定シリーズ』(ダイヤモンド社)です。
あまりにも有名なこの本ですが、実際に手に取ってみると、分厚くて独特の語り口に少し戸惑うかもしれません。
まずは本格的なワークシートに入る手前までの章を一気に読んでみてください。筆者の熱い言葉に何か感じるものがあるはずです。
大量のワークシートは億劫にならざるを得ない量ですから、早め早めに取り掛かることをおすすめします。
自己分析は、手間がかかるからこそリターンも大きい作業です。
焦らず、でも丁寧に、自分自身と対話する時間をとってみてください。
『ストレングスファインダー2.0』(日経BP)もおすすめです。
ウェブテストで自分の強みを教えてくれます。
まとめ:博士課程は客観的に自己を見つめるラストチャンス
この記事では、博士課程の学生こそ、なぜ自己分析をすべきなのかについて考えてきました。
博士課程の学生が、研究で常に忙しくしていることは、当の僕自身が最も理解しています。
しかし現実的な話として、一旦社会に出て組織に属すると、自分の人生についてじっくり考える時間やエネルギーを持てなくなることが多いです。
気がついたら周りの大多数に流されて意思決定してしまうなんて可能性も十分にありえます。
どんな進路を選んでも、自身の価値観や目標のアップデートのために、自己分析は生涯を通して続いていく作業でもあります。
博士学生という、ニュートラルな立場である最後の機会に、自己分析によって価値観の基礎を構築しておくことをおすすめします。
ぜひこの機会に、自分自身とじっくり向き合ってみてください。
では。