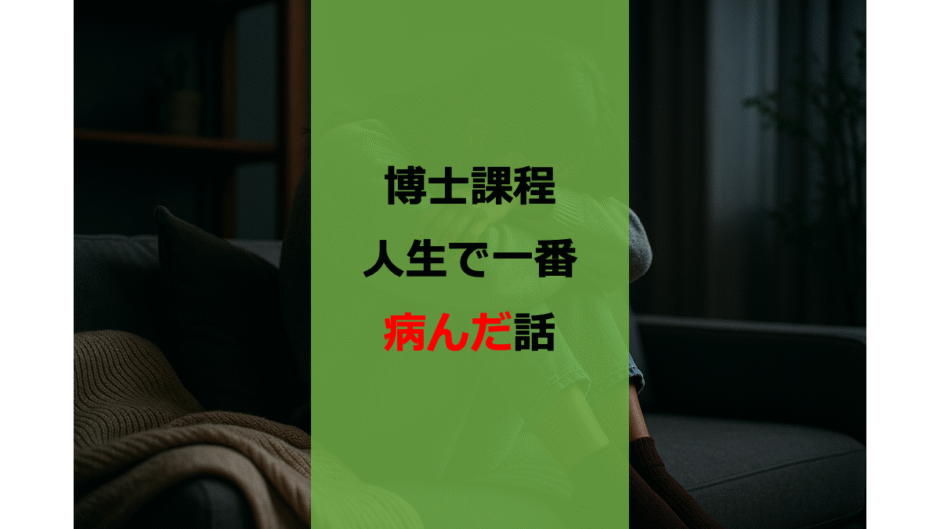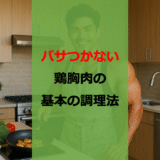こんにちは。ぱにです。

医学系の研究室で博士号取得を目指しています。
この記事は、本ブログのコンセプトと反する内容なのかもしれません。
それでも、正直に言います。博士課程の最初の2年、病みました。僕の人生で一番しんどかった。
症状としては深刻なものではなかったかもしれませんが、心療内科に診てもらっていたら間違いなく診断がついていたと思います。

実際に、数人の医師の友人が、当時の自分にちゃんと病院に行くように勧めてくれていました。
この記事では、その時期の僕に何があったのか、そして何を感じていたのかを、なるべく客観的に書いてみようと思います。
自分語りにはなりますし、普遍的なアドバイスは含まれていません。
それでも、僕自身の等身大の経験が、大学院生活に悩んでいる誰かにとって、何かしらの一助になれば嬉しいです。
実力もないのにプライドだけが膨らんだ修士時代
修士までに所属していた研究室では、正直、研究成果という点ではあまり苦労を感じていませんでした。
というのも、僕が引き継いだテーマは、すでに7割ほど完成していたものだったからです。
テーマの核となる新規性の高い発見は、前任者の先輩が見つけてくれていたので、僕の役割はその成果に肉付けをすること。
ある程度レールの引かれた中で、実験を積み重ねていけば及第点でした。
そんな環境のおかげで、学会やシンポジウムでも何度か発表の機会をもらい、運良く賞をもらえることもありました。
今思えば、心のどこかで僕は調子に乗っていたんだと思います。
当時の教授と研究結果の解釈や論文化の方針でもめて、食ってかかったこともありました。
でも冷静に考えれば、僕の実績はお膳立てがあってのものだったのに、それを忘れて自分がすごいと錯覚していたんです。
新たな刺激を求めて研究室を移籍
プライドだけが肥大していった僕は、当時いた研究室を飛び出すことを決意しました。
詳しい経緯は、また別の記事で書こうと思います。
最大の理由は、未知の分野に飛び込んで、自分の力でゼロから研究を立ち上げてみたかったからです。
当時の僕は、どこへ行っても自分の実力で切り拓いていけるという自信がありました。
いや、それは自信というより慢心に近かったのだと思います。
自分の興味に近く、かつ当時の研究とはなるべく離れた分野の研究室を見つけ、満を持して(のつもりで)その門を叩きました。
医学系研究室の特殊な構造
僕が移籍した先の研究室は、地方国立大学の医学部の上に乗っている基礎系の研究室でした。
こういった突出した研究力があるわけではない医学系研究室というのは、臨床の現場で働いてきた医師がキャリアに箔をつけるために、専門医を取ったあとに進学するという意味合いが強い場所でした。
実際、同じ大学院生とはいえ年齢は5〜7歳ほど離れていて、僕のように修士課程を終えてそのまま博士に進学したという人は一人もいませんでした。
彼らにとっては、大学院生である前にまず医師という立場があります。
医局に所属していたり、外勤で病院に出ていたりと、研究室に常駐していない方も多く、研究活動はあくまで“サブ”という印象を受けます。
そうした背景もあってか、研究室のカルチャーも、みんなで協力して大きなテーマに取り組むというよりは、それぞれが独立したテーマを黙々と進めるというもので、良くも悪くも周りに干渉しない研究室でした。

この特殊な雰囲気を知らないまま、研究室を決めてしまっていました。
研究をゼロから立ち上げることの難しさ
僕に与えられたテーマは、自分が希望した通り、ゼロから立ち上げるプロジェクトでした。
けれども、それは思っていた以上に過酷なスタートでした。
そのテーマに詳しい人は、研究室内に誰一人いませんでした。
教授でさえその分野には明るくなく、共同研究先からとりあえずと譲り受けたマテリアルだけがある状況でした。
しかも実験の性質上待ちの時間が長く、研究室にいながらはじめて、何もやることがないという非常事態。
培養や精製といった基本的な実験操作でつまずくことも多く、加えて、新しい研究室独自のルールや文化にも戸惑い、なかなか軌道に乗らない日々が続きました。
焦りはどんどん募りました。
メンターの先生に相談しても、テーマへの理解は浅く(おそらく興味もほとんどなかったのだと思います)、有効なアドバイスを得られることはありませんでした。
当初はもちろん、ゼロから研究を組み立てるなんて、すごく貴重な経験だと意気込んでいました。
でも、味方を作れないまま、相談相手もいないまま、すべてを一人で抱え込むようになっていきました。
誰とも話すことなく1日が終わる
次第に僕の博士研究生活は、一人で考え、一人で手を動かし、空いた時間をどうにかして潰すような毎日になっていきました。
初めのうちは、わからないことを周りの大学院生に相談することもありました。
ただ話をしていく中で、臨床が専門で基礎研究には不慣れな医師の先生たちにとって、僕の話はあまり興味がないのだと感じるようになり、相談しても意味がないと、どこかで決めつけるようになっていきました。
研究室で誰とも会話をせず一日が終わることも、珍しくなくなっていきました。
誰にも頼らず、あたかも一人でやれるかのように振る舞って、自分で壁を作るようになっていきました。
もしも、研究の悩みや進路の不安を気軽に話せるような、同じ立場の仲間が身近にいたら違っていたのかもしれません。

プライドが高すぎて自分でも笑えますね。
自分を責めるしか方法がなくなる
基本的な実験すら思うように進まない。なのにやるべきことがない。
忙しいよりも何もやることがない方が、時間だけが流れて自己否定に拍車がかかるということがよくわかりました。
テーマは始まったばかりで、今投げ出すわけにはいかない。
教授のことは尊敬していましたし、僕のことをよく考えてテーマを託してくださったのもわかっていました。
だからこそ、結果を出せないことに対して、申し訳なさを感じるようになっていきました。
しんどい。でも吐き出す場所はどこにもなかった。
行き場のない不安や苛立ちはすべて自分に向かっていきました。
将来への不安、研究の不透明さ、自分の無力さ。
「自分が弱いからいけないんだ」「もっと実力があれば」「博士なんて進まなきゃ良かったのかな」
こうした感情と4年も付き合っていかなくてはならないのかと思うと、気が遠くなるようでした。
ついに、壊れた
最初に異変を感じたのは、眠れなくなったことでした。
布団に入ればすぐ眠れるのは変わらずで良かったのですが、不安に襲われて2〜3時間で目が覚めてしまうようになってしまいました。
目が覚めたあとはなかなか眠れず、そのまま朝を迎えてしまい、毎日が寝不足で昼間にぼーっとしてしまうことが多くなりました。
次第に、日中にも異変が出てくるようになりました。
ふとした瞬間に、胸がぎゅっと締めつけられるような強い不安に襲われ、呼吸が浅くなり、なぜか涙が出てくるのです。
毎日のようにこの症状が出ていたわけではなかったですが、突然気持ちが沈み込むような感覚に襲われるので、自分でも戸惑いを感じていました。
休日になっても、気持ちが晴れることはありませんでした。
何かをしようという気持ちが起きず、特に興味もない動画をスマホで延々と見続けて、ただ時間だけが過ぎていく。ふと我に返ったときに残っているのは、自己嫌悪と虚しさだけでした。
これらすべてが典型的な鬱の症状であることは自覚していました。
しかし、病院に行くのが億劫だったし、応援してくれている家族にも知られたくなかったので、結局病院には行きませんでした。
なにより、メンタルが強いと思っていた自分が、そのメンタルを蝕まれていると認めることが怖かったのです。
まとめ:博士課程には魔物が棲む
この記事では、僕が人生で一番しんどかった時期について正直に書きました。
でもどうか、この記事の内容だけで博士課程を遠ざけないでほしいと願っています。
人は案外もろいものみたいです。
僕のように、いくつかの小さな歯車がずれただけで、あっさり壊れてしまうこともある。
僕自身、メンタルブレイクするとは夢にも思っていませんでした。
けれど、今振り返れば、どこかで立ち止まって誰かに頼ったり、自分を少し甘やかしたりすれば、あれほど追い詰めずに済んだはずでした。
だからこそ、この記事が鬱にならないための参考になれば、それ以上に嬉しいことはありません。

僕も今は元気に研究を続けています!
この最低の精神状態から立ち直るまでに何をしたかについても、また別の記事でお伝えできればと思います。
では。